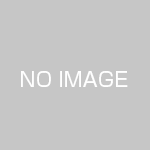【難民を助ける会|理事長ブログにて執筆】
3/5(土)トークイベント 震災から5年「帰る。帰らない。福島の葛藤」
東日本大震災の発生から間もなく5年を迎えます。改めまして犠牲になられた方々を悼み、そして今なお、それぞれのお立場やそれぞれの境遇の中で、東日本大震災が残した大きな困難と日々闘っておられる方々に、心からのお見舞いを申し上げます。
また発災当初より、私たちAAR Japan[難民を助ける会]の支援活動をお支えくださる支援者の皆さまに、また復興の現場で私たちにお力を貸してくださり、応援してくださる被災地の皆さまに、改めまして、心より御礼申し上げます。AARでは、今後も引き続き東北での支援活動を続けてまいります。どうぞ今後ともお見守りくださいますよう、お願い申し上げます。
東日本大震災に関するAARの活動報告や詳細は、本HPの「東日本大震災復興支援」ページ(リンク)をご覧ください。また、AARが活動の柱としております障がい者の方々への支援活動につきましても、同ページの野際紗綾子の寄稿文「東日本大震災被災障害者支援活動から見えた教訓と課題」>>(リンク 別ウィンドウで開きます )をぜひご覧いただけますと幸いです。
さて、本日は、発災当初より東日本大震災の被災地支援に携わってきた国際協力NGO・AARの理事長として、また支援活動に携わってきた個人として、東日本大震災の支援活動で得た気づきと学びとを2回に分けてお伝えしてまいりたいと思います。
第1回目の今回は、通訳・翻訳の限界とオーナーシップ・復興の主体・主役についてのお話です。AARでは、発災当初より、岩手、宮城、福島三県において緊急期の物資配布、障害者や高齢者施設・団体の支援や在宅避難者への個別支援などを行ってまいりました。私自身、2011年の3月下旬から福島県の相馬市を中心にAARの被災地支援に携わっておりました。発災直後は、緊張状態の中におり、特段意識することもなかったことですが、3ヵ月、半年と経過するにしたがって否応なく気づかされたことがあります。それが本日のテーマでもある、通訳・翻訳の限界と「聞こえる」という状態です。
3月11日の発災直後、AARの東京本部事務局では、状況がわからないまま、とにかく仙台方面を目指して順次出発していく初動部隊や、東京で後方支援に携わる多くの職員が誰ともなく、申し合せたように口にした言葉があります。「今回は、パスポートもVISAも飛行機の手配も必要ない、日本語も通じるから、通訳の心配もいらない」でした。それは母国を襲った、とてつもない大災害を前に、それぞれの不安を打ち消すための呪文のようなものでもあったのですが、他方、それは事実でもありました。
発災直後、援助物資の手配とともに、ガソリンの入手や、高速道路の通行許可証の取得などは予想以上に困難を極めました。しかし、それでもなお、現場は同じ国内である以上、未曽有の大災害とはいえ、見ず知らずの被災地にいきなり入ることになる海外の支援活動・オペレーションよりは、少なくとも言葉や地の利の点から、数段状況は良い筈、というのが一致した見解でした。
しかし、現実はそれほど甘いものではありませんでした。また私自身、「通訳がいらない」ことの意味を、時の経過とともに悟ることになります。被災地で、かろうじて開いている飲食店、給油のために立ち寄るガソリンスタンド、市役所の待合室など、あらゆる場所から被災者の方々の声や情報が聞こえてきます。誰が生き、誰が亡くなったのかという生き死にに関する情報、誰が去り、誰が残っているかという消息、補償金や将来への不安、自治体によって異なる行政の対応や機能の話、家族の近況や、難しい判断など、いずれも人の人生・生活のもっとも根幹にかかわることばかりです。
避難所となっている体育館のトイレでは、表で話を聞いたときには出てこなかった話が声を潜めて語られていました。そして毎日の新聞、テレビ、ラジオにも、被災者の方々の生の声、あまりに悲しく、あるいは壮絶な「そのとき」の物語、避難生活の日々の困難さを伝える声があふれていました。
その情報の洪水に溺れそうになりながら、思いを巡らせたのは、駐在した旧ユーゴ地域は言うに及ばず、出張で訪れたカンボジアやミャンマー、アフガニスタンやパキスタン、モザンビークやスーダン、インドネシアやインドなど過去に私自身が訪れた被災地で、聞いたと思っていた現地の声がいかに限られたものであったかという事実です。それらは英語ができる通訳を介して、聞こうとして聞いた質問に対する回答としての声であり、情報を集めようとして意図的に集めた情報の集積です。現地で読んだ新聞記事も、外国人が読むことを想定して書かれた英字紙か、特別に翻訳してもらった現地の新聞のほんの一部の記事です。
それをもって絶対的な「現地の声」としていた自分の了見の狭さに恥じ入る思いがしました。現地の言葉で現地の人々と接する、その地域を専門とする文化人類学者や地域研究者ほどではなくとも、私たちのように、次から次へと援助活動の現場を移動する国際協力要員であっても、活動の現場で密な人間関係は生まれます。一生もののお付き合いになるような特別の関係も稀ではありません。そうした関係性の中で入ってくる貴重な情報も数知れません。しかしそれは、無数に語られる人々の言葉のほんの一握りのことでしかなかったのだと、東北の被災地で、改めて意識するようになったのでした。
またある国際NGOでは、優秀な日本人職員を数多く抱えながら、東日本大震災の支援活動の計画・実施の主要部分は、ほとんどすべてが、初めて来日した日本語をまったく解さない外国人に委ねられていました。聞けば、東日本大震災の発生前に、アジア太平洋地域で大規模災害が起きた際には、オーストラリアのチームが統率者としてその世界大の組織全体の陣頭指揮を執ることが事前に決められていたといいます。もちろん、南太平洋の国々で起きる災害を想定したもので、よもや先進国・援助大国日本でこうした大災害が起きようとは誰も想像だにしていなかったときの話です。しかし、日本で大災害は起きました。
あれほど優秀な、経験に富んだ邦人職員が、日本語を解さない、日本の事情もまったく知らない外国人の下でローカルスタッフとして、ときに理不尽にも思える指示に従っている。なんという不合理・不条理・能力の無駄遣いと思いつつ、次の瞬間に、これまでの自分たちの活動を、背筋が凍る思いで振り返ったことは申し上げるまでもありません。南スーダンで、アフガニスタンで、スリランカで、それをしてきたのは、まぎれもない私、あるいは私たち自身だからです。
こうした指摘は、たとえば1980年代から90年代初頭のスーダン内戦を舞台に描かれたスクロギンズの『エンマの戦争』*にも出てきます。
「NGO、国連、国際機関を問わず、西側の援助機関が、スーダンやエチオピアの言語をほとんど解さず、この地の難民がもともと地元でどのような暮らしをしていたかの知識さえも持たない、大学卒業後間もない、無能にも見える欧米の若者たちが、管理職を務める優秀なスーダン人をさしおいて、現地の水準からは破格の給与で雇われていく様は、スーダン人の目から見れば、よく解釈して特定部族のえこひいきや優遇措置、悪く解釈すれば、新植民地主義以外のなにものでもなかった」(Deborah Scroggins, emma’s war, Love, Betrayal and Death in the Sudan, Harper Perennial 2002, pp66-67)
同じことは、東北の被災地でもあったはずです。地元のことは地元の方が一番よくご存知のはずなのに、東京や関西から駆け付けた、ときに東北初心者の人間が、海外の援助活動の専門家だから、あるいは、阪神淡路大震災や、新潟の中越沖地震の支援活動に携わった深い経験があるから、という理由で、中心になって活動の指揮をとっている構図も同様です。
他方で、別の気づきもありました。福島県の活動に際しては、ドナーとなった海外の財団やNGOに対し、彼らの助成や寄付を頂きつつ「ローカルNGO」としての私たちAARが現地で支援活動に直接携わったときです。福島県全体、あるいは東北一体を放射能汚染地と誤解し、現地に足を延ばすことをためらう海外の方もおられました。こうした安全管理の認識や、援助の手法は、海外のまさに危険地での支援活動に際し、国際職員の安全を確保するために、私たち外国人は現地に入らず、比較的治安の安定した近隣諸国から、指示を出し、実際の支援活動は現地の人にお任せするという「遠隔管理」方式の事業運営と全く同様です。
しかし、私や私たちに悲壮感や、お金だけで人を送らない組織に対して不満があったといえば、全くそんなことはありませんでした。そこはまぎれもなく私たちの国で、彼らは外国人。私たちが自ら動くのは当然であり、日本の震災を気にかけ、海外で募金活動をして資金を送ってくれる彼らに対しては感謝の思いしかありませんでした。これまで危険地などアフガニスタンやスーダンで地元の職員を残し、国外に退避することに後ろめたさを感じたことがたびたびありましたが、その必要はないのだと、少なくとも、私たちの退避を懸命にサポートしてくれることはあっても、決して非難することはないのは、そういう気持ちがあるからだと気付くことができました。
東日本大震災での支援活動は、国際協力NGOにとって、まさにこれまでの自分たちの活動を振り返るプロセスであったのです。(続く)
*『エンマの戦争』
エンマとは、スーダン南北内戦当時の一方の当事者であり、現在の南スーダン政府を構成するSPLA/SPLM(スーダン人民解放軍/解放運動 )の反主流派リエック・マチャル(Riek Machar)の妻となった英国女性エンマ・マクキューン(Emma McCune)のこと。彼女は援助関係者でした。2人の結婚直後の1991年、マチャルがSPLA創設以来のカリスマ的指導者ジョン・ガランに反旗を翻し、SPLA内の激しい武力紛争に発展したため、地元の人たちはこの紛争を「エンマの戦争」と呼んだのです。アメリカ人のジャーナリストの手によるこの書は、その歴史的・社会的洞察力からこの地域をフィールドとする援助関係者必読の書ともなっており、内外の研究者からも高い評価を得ている本です。
(2016年2月18日、同2月19日修正)