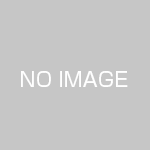5月6日は2022年に亡くなられたオシム監督の83回めの誕生日です。木村元彦さんが、分裂したボスニアサッカーの「正常化委員会」でのオシム監督の、文字通りの「闘い」を生き生きと、そして生々しく描いた『オシム 終わりなき闘い』。文庫版(小学館2018年)に解説「ユーゴスラビア人あるいはボスニア人としてのオシム」を書かせていただきました。文庫版は絶版のため、このHPに再掲いたします。
なお、木村元彦さんの『オシム 終わりなき闘い』(小学館2018年、全276頁)は、AMAZON Kindle版(693円・税込み)にて入手可能です。ぜひ、ご高覧ください。
*************
解説「ユーゴスラビア人」あるいは「ボスニア人」としてのオシム
『オシム 終わりなき闘い』を手に取りご覧になった皆さんへ
長 有紀枝
稀代のノンフィクション作家、木村元彦さんの手になるユーゴサッカー3部作『誇り ドラガン・ストイコビッチの軌跡』『悪者見参 ユーゴスラビアサッカー戦記』『オシムの言葉』。その完結編ともいえる本作『オシム 終わりなき闘い』。 サッカーファンや、木村ファン、その金言や生き方に魅せられたオシムファンは言うに及ばず、ボスニア紛争やバルカン地域を学ぶ学生、そして研究者にとっても、必読の書である。難民支援や平和構築に携わる実務者・研究者にとってさえ最良のテキストといえる。オシムや一家の体験を軸にたどるユーゴ紛争、離散した難民の生活と祖国への思い、オシムはじめ関係者がそれぞれの立場で語るボスニア紛争の真の原因と経緯は、歴史書や解説書を補完し、時に凌駕する、貴重な証言集でもある。エピローグで木村さんは第2章と4章を、「若い学究の方に参考にでもしていただければ書き手として望外の幸せ」と謙遜しておられるが、本書でオシムが、そしてそれに呼応した政治家や民族主義者が語り、行動したこと、さらに木村さんが独自の視点から切り取り、記録した出来事と証言の数々は、たぶん木村さんや私たち読者が考える以上に重要な記録だ。
私は、難民を助ける会(AAR Japan)という日本の国際協力NGOの職員として、1991年の旧ユーゴ紛争勃発時から1999年のNATOによるコソボ及びユーゴ空爆の時まで、現地駐在員として、あるいは出張者としてこの地にかかわってきた。NATOの空爆の折には、外国人がまとめて宿泊させられていたホテルの高層階から、まさに目の前をトマホークが閃光とともに横切り、発電施設を空爆するさまも目の当たりにした。その後、研究者として取り組んだ博士論文では、オシムの半身ともいえるアシマ夫人も当事者であったサラエボ包囲や、スレブレニツァの虐殺の首謀者とされる人物やその家族と面識があったことから半ば逃れられない定めのようにスレブレニツァの虐殺に取り組んだ。前半を実務家として、後半を研究者として触れたこの地は、まさに幾世代にもおよぶ憎悪の渦巻く土地であり、一連の木村作品に登場する、サッカーチームのホームや選手の故郷は、単なる地名ではなく、木村さんが絶妙のタイミングで解説をはさんでおられるように、虐殺の現場の地名であったりする。オシムの故郷、グルバヴィッツァもまたしかり。1995年春、視察中のグルバヴィッツァで「ヒュン」という空気を切り裂く音とともに、すぐ近くの廃墟に銃痕が刻まれたことを思い出す。セルビア側のスナイパーのいる方角からではない。犯罪の量に違いはあるが、質においては三民族同様といわれる三つ巴の戦いの中で、民間人を狙うスナイパーはいずれの側にもいて、犠牲者もまたいずれの民族にもいたのである。
さて、本書の主題である「正常化委員会」の背景については、既に卓越したジャーナリストでもある木村さんが詳述しておられるが、これらにまた別の光を当てるために、平和構築や国際協力の視点から解説を加えてみたい。
本書の舞台となった2013年前後のボスニア。1995年の紛争終結からおよそ20年が経過した紛争から平時に向かう「移行期社会」である。一般に、移行期社会とは、その地域にとって歴史的な分断期であり、平時であれば存在するはずの社会的な正義に対する共有された認識が欠如した社会である。チャップリンの映画『殺人狂時代』に登場する「一人殺せば殺人者、大勢殺せば英雄(One murder makes a villain; millions a hero)」という言葉が象徴しているように、人の命の軽重、殺人や犯罪に対する法的評価、あるいは人々の許容度がことごとく変わる時代の境目でもある。そして長引く紛争が暴力を拡散させる連鎖の中で加害者と被害者の関係は、固定されることがない。それゆえ、紛争後の社会においても加害者・被害者が混在し、明確な線引きが不可能な状態にある。
さらに、さかのぼる歴史の終着点により、加害民族と被害民族が時と場所を変えて入れ替わる。ボスニアはその歴史が示すとおり、こうした移行期社会の特質をそのまま体現した社会である。
《民族紛争の特徴》
「血で血を洗う」という表現もなされる民族紛争。戦前は、私的な空間においても公共の空間においても平和裡に共存していた隣人や職場の同僚、学校の友人知人がある日を境に敵や加害者となる。もちろんそこには、異民族の友人知人を守り抜こうとする人が少なからず存在する。しかし彼らは早い時期に標的とされるか、見せしめのように、ことさら残忍な方法で葬りさられ、紛争前の日常を守ろうとする人々は水面下に押しやられる。
そして被害者のみならず加害者さえも、相手に裏切られたという意識を抱いている(あるいは植え付けられている)。戦争の原因や被害についての真実や事実が捻じ曲げられ、否定されているとの思いを誰もが抱く一方で、自身や帰属集団による加害行為については、否定あるいは過少評価し、またはあくまでも自己防衛のためであったと主張する。
本書で紹介されたジャーナリストの言葉がまさにそれである。「ボスニア紛争を語る上で重要なのは3つのどの民族も自分たちこそが被害者だと考えているということだ。それぞれが他の民族に行なった加害性については微塵も意識していない」(97頁)。
《国際社会の介入》
こうした民族紛争に対して、すべての紛争とはいわないが、多くの紛争に対し、国連や安全保障理事会の常任理事国、加盟国、地域機関やNGOが介入・支援する。難民や国内避難民、被災者が命をつなぐための人道支援、国連平和維持活動(PKO)、有志連合による武力をともなう「人道的」介入。しかし現在のシリア情勢をみても明らかなように最も望まれるものが、紛争そのものを終結させる政治的解決への取り組みである。
1992年春から1995年11月の3年半に及ぶ紛争中、国際社会の様々な主体が紛争の鎮静化や、紛争そのものを終結させる和平調停を試みた。前者の試みとしては、ニュルンベルク、極東国際軍事裁判所以来、およそ50年の時を経て、1993年に設置された旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ICTY)がある。紛争の最中にあまりに甚大な国際人道法違反や、凄惨な民族浄化の実態を憂慮し、戦争犯罪人の処罰が、紛争の終結に大きく寄与することを想定して、国連の強制措置の発動である国連憲章七章下の安保理決議によって設立されたものだ。 戦争を終わらせようとする試みも繰り返された。しかし協定が結ばれては破られ、いずれも暗礁に乗り上げたまま、最終的にボスニアの3勢力を和平に導いたのが、戦後のボスニアの設計図ともなったデイトン和平合意である。
1995年11月にオハイオ州デイトンで協議・合意され、12月パリで正式に発効したデイトン和平合意は一言でいうなら「停戦には成功したが、国造りには失敗」したという評価に集約されるだろう。19世紀の列強による植民地支配にも例えられるほど、強力な権限を国際社会の代表である「上級代表(OHR)」に与え、その強権の下、単一国家を維持したまま、ボシュニャク・クロアチア人による「ボスニア連邦」とセルビア人の「スルプスカ共和国」という2つの「エンティティー(政体・自治政府)」に軍、警察権などを含む広範な権限を付与している(その後、軍は統合)。デイトン和平合意は、新生ボスニアを多民族・多文化の共生社会としつつも、国家の構成民族を、ボシュニャク人、クロアチア人、セルビア人の3民族に限定するという矛盾を選択した。3人の大統領はボスニア・ヘルツェゴビナ全域に責任を有するものの、各民族集団から選出され、すべての国民に対する責任を負っているわけではない。3民族の融和・共生を特別視するあまり、融和に欠かせない接着剤、緩衝材として機能したはずの、「ユーゴスラビア人」や「ボスニア・ヘルツェゴビナ人」など特定の民族に所属することを望まない人、ユダヤ人やロマなどの少数民族が政治の表舞台に立つことは叶わない。オシムに代表されるような、既存の民族の枠を超える、戦後の国造りの鍵となる「ユーゴスラビア人」という概念は法的に存在の余地がない。そうした背景のもとに臨んだ、正常化委員会でのオシムの仕事である。
デイトン和平合意の主役は、ある意味、当事者のボスニア3民族ではなく、絶大な権限をもつ上級代表といえる。国際協力に携わる者として、自戒を込めていうが、それが国連だろうと、国の援助機関やその下で働くコンサルタント会社であろうと、国際機関やNGOであろうと、洋の東西、規模の大小、分野を問わず、資金を出し、それぞれの目的達成のために外から介入する外部者が主役になりがちだ。本末転倒であるが、まぎれもない現実である。
デイトンが作り上げた新生ボスニアもまたしかり。しかしだからこそ「正常化委員会」におけるオシムの功績は特筆に値する。それを融和と呼ぶかどうかは別にしても、3民族の協働、協力体制を、国際社会ではなく、生粋のボスニア・ヘルツェゴビナ人であるオシムが主導した、そのことにとてつもなく大きな意義がある。
オシムが生きてきた時代は、木村さんが本書に書いたとおり、セルビア人でも、クロアチア人でも、ボシュニャク人でもなく、ユーゴスラビア人もしくはボスニア人(多民族国家ボスニアという国の人間)として生きることは多大な困難を伴う。のみならず、時に命懸けの行為であり、生き方である。
この地が生んだノーベル文学賞作家、イヴォ・アンドリッチはそうした人々を「余所者(よそもの)」と呼んだ。民族間の敵愾心をあおる人々、戦争を続けようとする勢力にとって、どちらの側にもつかない、かといって、中立を掲げる外国人・部外者ではない、内なる「余所者」はあまりに厄介な存在だ。特に影響力のある内なる「余所者」はユーゴ紛争の初期に、あらゆる勢力から狙われ、殉教者にされた。つまり、紛争を始めたあらゆる勢力にとって「真の敵」は、異民族ではなく戦争に異を唱える同胞、それも影響力のある同胞なのである。その「余所者」が政治家であれば、政敵としてまだわかりやすい。しかし、オシムは、政治家ではない。だからこそより危険な「余所者」なのである。
木村さんは、「戦略家」としてのオシムの一面も描きだした。民族問題を政治的空間のみならずあらゆる生活領域に持ち込むことが常態化しているデイトン後のボスニアにおいて、サッカーという、たぶんこの地にとってもっとも重要なスポーツの世界にそれを持ち込ませないという奇跡が実現したのは、彼が、単なる理想主義者であるからではなく、まさにサッカーでみせたような「戦略家」であったからだろう。
イビツァ・オシムという人が存在しえたということ、彼が存在する空間がサッカーというスポーツにあったことは、暗雲ただようこの国や地域の未来に光明を見る思いがする。
ボスニアの、オシムの闘いは終わらない。木村さんのあとがきにあるとおり、かろうじて、国際社会の監視の目の中で均衡を保っているボスニア情勢。その重しであるEUそのものがボスニアにかかわっていられなくなった時、何が起きるのか。戦後はや20年、あるいはまだ20年。「民族融和」や「和解」「共存」という言葉を軽々しくは口にできない険しい空気に包まれる地域があり、人々がいる。スレブレニツァのみならず、虐殺の現場が日々の生活空間に存在し、いまだ多くの行方不明者、家族のもとに帰れない死者たちがすぐ近くの山中で朽ちている。そんな世界でサッカー、そしてオシムの存在は、分断された国をつなぐ希望であり続けている。
2018年5月6日 オシムの77回目の誕生日に(木村元彦2018年『オシム 終わりなき闘い』小学館 文庫版318-326頁所収)
*木村元彦さんの『オシム 終わりなき闘い』(小学館2018年、全276頁)のAMAZON Kindle版(693円・税込み)はこちら>>>