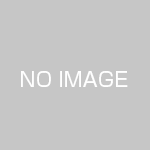7月11日はスレブレニツァの追悼記念日です。これに先立ち、6月末日に発行された、国際安全保障学会発行の『国際安全保障』第50巻第1号(2022年6月)の「持続的な平和(Sustaining Peace)の実現に向けた取り組みの現状と課題」特集号に、「ボスニア・ヘルツェゴヴィナの平和構築再考―デイトン和平合意25年後の教訓」を書かせていただきました。
「戦争を終わらせるために設計されたもので、国家建設のためではない」と言われるデイトン合意。その合意から四半世紀が経過した現在、ボスニアは1995年の紛争終結以来、「最悪のセキュリティクライシスのただ中にある」と言われます。本論ではクラウゼヴィツの「戦争とは他の手段を用いて行われる政治(外交)交渉の継続である」というテーゼを反転させた第4代上級代表アシュダウンの警句ー「デイトン和平合意後のボスニアは他の手段を用いて行う戦争の継続である」ーを出発点に、国際社会の平和構築の実験場と揶揄されてきたボスニアの抱える問題について、デイトン和平合意やその交渉プロセスに立ち返って検討しました。
4月初旬が締め切りでしたが、本当に苦しみ抜いた原稿です。ご依頼を頂いたのは昨秋でしたのに、締め切りを守れず、特に今号の編集主任の篠田英朗先生や、編集委員会の先生方に多大なご迷惑をおかけしてしまいました。遅筆の言い訳すべきではありませんが、備忘録的にまた自戒をこめて事情を記しますと、同時期、日常業務に加えて他の研究会での発表や別の原稿にも追われていたこと(これはどなたも一緒ですから言い訳にすらなりませんが)、またボスニア紛争とデイトン和平合意について、ある分野・局面については知りすぎ、またある面については、知らなさすぎる、という自分の知識のアンバランスさを痛いほど自覚していたこともあり、どの切り口で書くのか、何を論点とするのか、先行研究の資料収集は行いつつも、焦点や視角が一向に定まらなかったこと、そしてやっと取り掛かろうとした矢先のロシアのウクライナ侵攻で、今度は別の仕事が次々と降ってくる中で、それらと同時並行になったこと。
最終的には、ご依頼の趣旨から外れることは承知しつつも、膨大に集めた英語文献にはほとんど手が付けられないまま、デイトン和平合意交渉の中心にいた米国務次官補R・ホルブルックの回顧録(Richard Holbrooke, To End a War, Modern Library 1999)を手掛かりに論考を進めることになりました。ホルブルックが回顧録で初めて明かした興味深い事実も多数あり、歴史書としての評価は別かもしれませんが、個人的にはデイトン和平合意交渉を検討する上で、また旧ユーゴスラヴィア国際刑事裁判所(ICTY)のいくつかの判例を検討する上で非常に重要な一次資料となりました。
執筆自体は、なかなか焦点が絞れないまま、いつも通り、長めに書き連ねそこから字数にあわせてそぎ落とす形式をとりましたが、この手法含め反省点の多い原稿です。字数制限のある論文には、字数にあった構成があること、その長さ、字数に応じた内容量、論点にしないと整合性がとれなくなる、ということも改めて痛感した原稿で、この教訓はこの論文脱稿後に期せずして続いた、『世界』7月号と『中央公論』8月号の拙稿には生かしたつもりですが、どうでしょうか。今後も向こう1カ月にウクライナと難民問題で、2本の原稿の締切があり、8月には大小さまざまな講演と、秋の学会発表の要旨の作成があります。どのような切り口で、どのように論点を切り分けていくのか、個人的にはまさにチャレンジングな挑戦ですが、また現場で活動できないもどかしさもありますが、ウクライナ紛争をはじめ、この時代の課題に、自分なりに向き合い、対峙する方法として真摯に、後悔のない原稿を送り出したいと思います。
なおこの間、メディアの取材も相次ぎました。短い談話もありましたが、多くがまとまったインタビュー形式で場合によっては短い論文を書くような形態も複数あり、文字通りその対応にも忙殺されました。それゆえ、お断りさせていただいた取材も、取材依頼のメールそのものにお返事すらできなかったものもございます。この文章を読んでいただけるとも思えませんが、失礼を心からお詫びします。またこの間、講演会も相次ぎました。以前から決まっていたものもありますが、多くはウクライナの難民問題に関連したものです。一つひとつ真摯に臨んだつもりですが、ある学会のパネリストは、ほとんど全く準備が整わないまま、心ここにあらずのような状態で臨む結果となってしまいお詫びの言葉もありません。自分のキャパを超えてお仕事を受けるとこういうことにもなる、というのも痛い学びであり、教訓です。
さて、余談ですが新学期早々大学院のゼミでは、毎週、「書けない、まだ書けない」を連発してしまったため、修士論文の中間発表を控えたゼミ生たちから、「先生も書けないことがあると知ってちょっと安心した」(いつもです)「苦しんでいるのは自分だけではないと知って心が軽くなった」という予想外の反応。この駄文も、現在論文執筆中の大学院生に向けても記しています。ゼミ生には、いつも言っていますが、論文は「書けない書けない」と言っている間は本当に書けません。「書ける、書ける、私には書ける」という暗示も大切。そして、読者としての自分が一番読みたいものを書きましょう。(かくいう私は、今、「依頼」ではなく、「主体的に」もっとも書きたいのは、難民を助ける会の、今後のウクライナの活動に直結する地雷問題に関する文章、そして数年来の懸案であるスレブレニツァに関連する一般書の原稿です。長くお待ち頂いている編集者の方にあわせる顔がない心境ですが、心を強く持って必ず書いていきます。)
さて、もう一つの大事な追記です。夜中に張り詰めた作業をして明け方まで数時間という時。翌日の仕事を考えて少しでも長く睡眠時間を確保せねばならないのに、神経がたかぶって眠れない時、助けられた本と薬があります。本とは、昆虫写真家・森上信夫さんのエッセイ集『オオカマキリと同伴出勤―昆虫カメラマン、虫に恋して東奔西走』(築地書館2020年)。森上さんは、立教大学の元職員。私がいる大学院・21世紀社会デザイン研究科を担当する独立研究科事務室にもお勤めでした。昨年早期退職されて、今は独立されておられますが、本書は、大学職員と徹夜の連続の昆虫カメラマンとして二足の草鞋を履いた兼業カメラマン時代の出来事をつづったもの。気分転換というより、人としてのまっとうな、何か大切なものを思い起こさせてくれる本で、1話読むうち、にっこり、ほっこり、緊張もほぐれ、自然に眠りにつくことができました。もう一つは、近所の内科の先生から、肩こり対策でいただいている漢方薬「葛根湯」です。風邪の引きはじめに適した漢方薬として知られていますが、これをお湯に溶いて、寝る前に飲むと、強いお酒より効き目大、翌朝も爽快です。あくまで個人の感想ですが・・・。