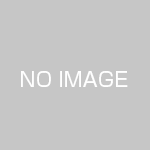目次
移民問題と、無意識に、あるいは意識的・意図的に境界がぼかされ、混同される対象に難民問題がある。イメージや認識と実態との落差・ギャップが激しいのも難民問題であり、異なる言説が鋭く対立するのも難民問題である。
そこで本稿ではまず、誤用や転用が多い「難民」の狭義・広義の定義を整理し(1節)、「先進国に難民が押し寄せている」というイメージと現実との乖離を数字で確認する(2節)。次に日本の難民受入れの歴史を概観した上で、「日本には本当の難民がいない・来ない」という言説の背景にある、外国人労働者による難民認定制度の「濫用・悪用」の実態と、そうした人々に支えられて成立している日本の労働市場を、私たちの日々の暮らしとの関連から考える(3節)。最後に「難民に冷たい日本」批判は、単純な難民認定率だけを根拠とするなら不当だが、数少ない「本当の難民」さえ不認定にされる厳しい日本の審査基準(4節)や、第三国定住による難民受入れの極端に少ない実績を基準にするなら反論できない現実を注視し、提言につなげたい(5節)
難民問題は、誰によって、どのような視点から論じられるべきものなのか。難民問題をどのように考えるかは、たぶんに政策的決定の問題である。しかし狭義の「国益」、自国の利益を最優先に難民政策を決めていては、日本国憲法前文にある「国際社会において名誉ある地位を占める」ことなど、とうてい不可能だろう。もとより、東日本大震災において、一六三の国や地域、そして四三の国際機関から支援の申し出を受けた(外務省調べ)国にとって、自国の利益のみで行動する、あるいは国際的責務を果たさない、という態度は、もはや選択肢にないはずである。
難民問題の議論は、論客や実務者が、それぞれが拠って立つ事実やデータをもとに主張を展開するため、それぞれ説得力を持つ一方で、時に一面的な、あるいは断片的な議論に陥りやすい。必ずしも事実の積み重ねが真実となるわけではない。重要なのは、複合的・多面的に状況を見極め日本の難民政策に収斂していくことではないだろうか。
難民問題に限らず、国際協力にかかわる政策とは、人道的配慮と「国益」双方のバランスから考えられるべきものであり、どちらにどれくらい比重を傾けるかは、あるいは両者の間でどこに均衡点を見出すかは、時の政治の役目である。そして民主主義国家において、その政治にもっとも影響を及ぼしうるのは、国民、選挙民の声そのものである。この小論をつうじてその均衡点を探すための一つの視座、ヒントを提示できれば、と考えている。
1 「難民」とは何か――定義
移民問題を専門とする国連機関、国際移住機関(IOM)によれば、「移民」とは、当人の①法的地位、②移動が自発的か否か、③移動にいたる理由、④滞在期間、のいかんにかかわらず、本来の居住地を離れて、国境を越えるか、一国内で移動している、または移動したあらゆる人を指している。その意味で、難民も移民の一部と言うこともできるが、「難民」とは私たちが日常用語で使用する、「行き場のない人」、あるいは「移民の一種」というような漠としたものではなく、明確な定義がある法的な概念である。
難民条約上の定義
国際社会に共通の難民の定義は、一九五一年に採択された「難民の地位に関する条約」(難民条約)と一九六七年の「難民の地位に関する議定書」(難民議定書)にある。
この条約上、難民とは、「人種、宗教、国籍、若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」をいう。言い換えると、難民として認定されるには、十分に理由のある「迫害」の恐怖から国境を越えていなければならず、その迫害の理由とされるのは、人種、宗教、国籍、特定の社会集団、政治的意見の五要件のみである。非常に限定的であり、紛争や自然災害、テロなどの危険から身を守るために命からがら他国へ逃がれた人や集団についての記載はない。
そもそも第二次世界大戦後の混乱期に欧州で生じた難民問題に対処するため生まれた難民条約は、ナチのジェノサイドによる大量のユダヤ難民や、共産圏からの難民など、東西のイデオロギー対立を色濃く反映した条約であり、起草過程において、大規模な難民流入は想定されてはいたものの、それらはあくまで政治的な難民であって紛争を逃れた人々ではなかったのである。
二〇一八年一〇月現在、日本を含む一四二カ国が難民条約と難民議定書双方に加入している。難民条約には、難民の定義と滞在国の法令順守という難民の一般的義務とともに難民の権利が詳細に記されている。他方、具体的な難民認定手続きや方法、判断基準の規定はなく、締約国に委ねられている。
広義の難民
難民条約が射程の外に置いた紛争に起因する大量の難民という問題に早くから向き合い、より現実的な対処をしてきたのがアフリカ諸国である。
アフリカの多くの国々が、植民地支配からの独立とともに難民条約の締結国となったが、難民問題がアフリカ諸国に共通の重要課題であることから、アフリカ統一機構(OAU、現アフリカ連合=AU)が積極的に取り組み、一九六九年には、OAU難民条約を締結している。難民の法的定義を拡大したこの条約は、難民条約の定義を踏まえた上で、外部からの侵略、占領、外国による支配、出身国の一部または全体の社会的秩序を著しく乱す事件ゆえに、国境を越えざるをえなかった人々も難民の定義に含むとした。「広義の難民」である。
途上国を中心に発生している「広義の難民」に特徴的なのが、難民認定の方法や待遇である。日本や欧米、豪州などの先進諸国での難民認定は、申請者一人ひとりに対する難民審査が基本である。他方で、大量の難民の直接の受入れ国となった発展途上国においては、個人個人の難民認定作業は物理的にも財政的にも不可能である。そこで、こうした負担の大きさや緊急性を理由に資格審査をUNHCRに委任する、あるいは個別に審査することなく、国を逃れてきた状況や背景から、その集団全体の難民性を判断し、認定する方法がとられている。「プリマ・ファシ」手続きと呼ばれる難民の地位の集団認定手続きである。
先進国では個別の審査を経て認定されると、難民条約に規定されたとおり、他の一般市民同様の生活を送ることが、少なくとも名目上は可能となる。しかし、途上国の難民の多くは、受入れ国政府によって就労が制限され、大規模難民キャンプでの居住が義務付けられるなど、保護と引き換えに隔離・管理政策の対象となることが多い。
2 イメージと実態の落差
今日、世界にはいったいどれほどの難民が存在するのだろうか。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の最新の年次報告書『グローバル・トレンズ2017』(二〇一八年六月公開)によれば、二〇一七年末時点で、紛争や暴力、迫害により強制的に家や故郷を追われた人の数は六八五〇万人。二秒に一人、一日あたり平均四万四五〇〇人が強制的に家を追われ、地球上の一一〇人に一人が避難を余儀なくされている計算だ。史上最多の人数で、三〇年前の一九九七年の統計三三九〇万人の二倍を超える。
内訳は、難民同様の困難に置かれているものの、国境を越えていない(あるいは超えることができない)国内避難民四〇〇〇万人、難民二五四〇万人、庇護申請者(難民として国際的な保護を求めている人々)三一〇万人である。
国内避難民の上位三カ国
| コロンビア | 七七〇万人 |
| シリア | 六三〇万人 |
| コンゴ民主共和国 | 四四〇万人 |
難民出身国の上位五カ国
| シリア | 六三〇万人 |
| アフガニスタン | 二六〇万人 |
| 南スーダン | 二四〇万人 |
| ミャンマー | 一二〇万人 |
| ソマリア | 九八万人 |
この五カ国に世界の難民の六八%が集中し、とりわけシリアは全人口の三分の二(一二〇〇万人)が難民、国内避難民、庇護申請者である。世界人口に子どもが占める割合は三一%だが、難民では五二%が一八歳未満の子どもだ。難民問題と関係の深い無国籍者は各国の集計上は七五カ国三二〇万人だが、実際には約一〇〇〇万人と推定される。
国連難民高等弁務官のフィリッポ・グランディは近年の欧米、豪州への多数の人々の流入は、あたかも豊かな先進諸国を「難民危機」が襲っているかのようなイメージを作り出したが、これはまったくの誤解であると主張する。先進諸国に暮らしている、または庇護を求めた難民は家を追われた人々の一割にも満たない(五四〇万人)。世界の難民・避難民のうち、六割近くは国境を超えることすらできない国内避難民が占め、しかも難民のうち五人に四人が隣国に、一〇人に九人が母国に近い地域内に留まっているからだ。パレスチナ難民(五四〇万人)を除く難民(一九九〇万人)の八五%が発展途上国に、うち四九〇万人が後発開発途上国にいる。影響を最も受けているのは、資源の稀少な貧困国、中所得国やそのコミュニティであり、決して先進国ではないのである。
難民受入れ上位八カ国
| トルコ | 三五〇万人 |
| パキスタン | 一四〇万人 |
| ウガンダ | 一四〇万人 |
| レバノン | 九九万八九〇〇人 |
| イラン | 九七万九四〇〇人 |
| ドイツ | 九七万四〇〇人 |
| バングラデシュ | 九三万二二〇〇人 |
| スーダン | 九〇万六六〇〇人 |
3 「日本には本当の難民はいない」という言説
難民といえば、食べるものもろくにない、やせ細ったアフリカの子どもたちか、逃げ惑うシリアの人々を想像し、遠い世界の出来事と感じるためか、そもそも日本に難民が存在するということ自体に驚きをもつ人もいるようだ。しかし日本にも四〇年前から数は少なくとも難民が暮らしている。
日本には、①狭義の難民(条約難民)、②広義の難民、③第三国定住による難民と、三つのカテゴリーの難民が存在する。②・③はそもそも国籍が限られる概念ではないが、日本の場合、歴史的経緯と政策により、②の対象はすでに受入れが終了しているインドシナ三国(ベトナム、ラオス、カンボジア)からの難民のみ、③はタイとマレーシアの難民キャンプにいるミャンマー難民のみが対象の限定的取組である。歴史的経緯から振り返る。
インドシナ難民の受入れ
一九七五年四月末の旧南ベトナム政権崩壊以降、漁船など小型船で脱出を図るベトナムからのボート・ピープルが激増。日本でも一九七五年から難民の漂着が始まり、ピーク時の一九七九~八二年にかけて、四年間で計四〇〇〇人を超す難民が流入する事態となった(筆者が理事長をつとめる難民を助ける会も、「インドシナ難民を助ける会」として一九七九年に発足した)。時を同じくしてラオスとカンボジアでも情勢が不安定化、カンボジアのポルポト派の虐殺から逃れる難民も加わり、インドシナ三国からの難民が深刻な国際問題となった。当初日本では、ボート・ピープルの一時滞在のみを認めていたが、内外の意見や要請に応え、政府は一九七八年四月二八日の閣議了解によりベトナム難民の定住を認めた。当初はベトナム難民のみ、かつ人数も制限されていたが、後にこれを撤廃、対象もラオス、カンボジア難民へと広げ、一九八〇年の閣議了解では、家族の呼び寄せを認めるなど条件も緩和された。その結果、受入れが終了する二〇〇五年までの二七年間で一万一三一九人のインドシナ難民が日本に定住することとなった。
インドシナ難民の受入れに際しては、個別の難民性の審査は行なわれず、まさに「プリマ・ファシ難民」であるが、国内での処遇は条約難民に準じるとされた。
難民条約加入と条約難民
インドシナ難民に直面した一九七〇年代後半の日本では、難民問題への関心も高まり、一九八一年六月の通常国会において、難民条約・議定書双方への加入が承認され、翌八二年の一月一日をもって日本は、同条約・議定書の締約国となった。難民条約への加入に際し、政府は従来の出入国管理法令を改正、新たに難民認定制度を導入するとともに、名称を「出入国管理及び難民認定法(入管法)」へと改称し、難民の認定は法務省入国管理局の所管となった。
一九八二年の難民条約加入・難民認定制度導入から昨二〇一七年末までの申請数は六万六七五件、うち難民と認定された人(条約難民)七〇八人、認定はされなかったものの人道上の配慮を理由に在留を認められた人が二五八八人である。
第三国定住難民
第三国定住とは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を、当初の庇護国から新たに受入れに合意した第三国へ移動させ、難民は移動先の第三国で庇護やその他の長期的な滞在権利を与えられる制度である。UNHCRはこの方法を、難民問題の恒久的解決策の一つと位置づけ、各国に推奨してきた。難民問題に関する負担や責任を国際社会において適正に分担するという観点から重視されている。
こうした動向を踏まえ、日本は、「国際貢献及び人道支援の観点から、アジア地域で発生している難民問題に対処するため」(外務省)として、二〇〇八年一二月の閣議了解で、第三国定住によるミャンマー難民の受入れを三年間のパイロットケースとして決定、二〇一〇年に受入れを開始した。当時アジアで初の第三国定住であった。その後二年間の延長を決定、二〇一四年度までタイの難民キャンプに滞在するミャンマー難民の受入れを行なった。二〇一五年以降も閣議了解及び難民対策連絡調整会議決定に基づき、第三国定住による難民の受入れを継続している。ただし対象は引き続き家族単位のミャンマー難民に限定されている(マレーシアに滞在するミャンマー難民及びパイロット事業で受入れたタイの難民キャンプに滞在する難民の親族対象)。二〇一七年末までに受入れた第三国定住難民数は、合計三九家族一五二人である。「国際貢献」というにはあまりに小さすぎる数字である。
日本には「本当の難民」はいないという言説の背景
日本での難民認定申請者数は、制度を待ち望んでいたと思われる初年度一九八二年の五三〇人を例外とすると、翌八三年から九五年までの一三年間の申請者は、おおむね四〇~五〇人平均で推移していた。条約難民と認定された人も、最初の四年間の合計は一七一名(同時期の申請者総数は六六五人)。認定率としては二五・七%である。
制度がスタートして一五年目、一九九六年に申請者数は一四七人と初の三桁台に乗る。次の大きな山は、二〇〇六年、前年の三八四人から二・五倍の九五四人に。その後二〇一一年までの四年間は一〇〇〇人台が続くが、二〇一二年以降、二五四五名、三二六〇人(一三年)、五〇〇〇人(一四年)、七五八六人(一五年)と増え続け、二〇一六年には一万人を突破、昨年はほぼ倍増の一万九六二九人となった。
では、これらの申請者はどこから来ているのか。二〇一七年度の申請者の国籍は八二カ国におよぶが、フィリピン、ベトナム、スリランカ、インドネシア、ネパールの上位五カ国出身者だけで、申請者総数の約七割を占める。他方でUNHCR報告書の同年の難民出身上位五カ国(シリア、アフガニスタン、南スーダン、ミャンマー、ソマリア)からの申請者は、わずか三六人にとどまっている。世界の難民と日本の難民申請者の出身国には明らかな乖離がみられるが、これは実は至極当然のことである。遠く離れた島国日本に来るためには、飛行機に乗らねばならない。パスポートを取得し、高額な航空券を入手して空港に行くことなど、地続きの隣国への脱出が精いっぱいの大多数の難民や、国外に脱出することすらままならない国内避難民にとっては到底不可能である。なけなしの財産をはたき、親類縁者から借金するなど様々な手段を使って脱出が可能になった一握りの人々にとってさえも(ほかに選択肢がなかったり、親族が日本にいたりする場合は除き)、英語が通じず、難民に冷たいという悪評のある日本は、決して選びたい国ではないのである。
さて申請者急増の理由とされるのが、日本での就労を目的とする外国人労働者による難民認定制度の「濫用」や「誤用・悪用」であり、その契機として指摘されるのが二〇一〇年三月に導入された難民支援策である。これは入国時に短期滞在や技能実習、留学などの在留資格を持つ正規滞在者が難民申請を行った場合には、申請から六カ月経過後、認定手続き完了まで就労を認めるというもので、本来は「難民認定手続き中の生活の安定に配慮して」導入されたものだ。しかしその後、東南アジアからの難民申請者が急増、全申請者の八割を占めるにいたった。このため二〇一五年に運用制度の見直しがなされたが、再申請者を対象としたため、初回申請者の抑制にはつながらなかった。申請者の急増に審査が追い付かず審査期間が長期化し、審査官の面談などを含む一次審査に平均一〇カ月、不認定後の不服申し立てに対する審査には二年近くかかることとなり、法務省は、二〇一八年一月、「更なる見直し」として、難民申請後二カ月以内に書面審査のみで申請者を選別、審査を短縮する試みを始めている。
難民審査の大きな阻害要因となっている認定制度の濫用だが、この背景に、申請手続きにたけた仲介業者、ブローカーの存在が指摘されている。空港近くの日本語学校が組織ぐるみで制度の悪用を指南し、ブローカー役を務めている例もあると聞く。こうしたブローカーに対する批判は多いが、果たして問題はブローカーの存在だろうか。
ブローカーの暗躍は事実ではあるが、ブローカーや就労目的の「偽装難民」批判に終始しては本質を見誤まる。ブローカーは特定の政治的意図をもった犯罪集団ではない。その目的は、難民制度の悪用でも日本社会のかく乱でもない。金儲け、ビジネスであり、外国人労働者のあっせんは、カネになるのである。ではなぜビジネスとして成立するのか。それは、難民認定制度を悪用してでも合法的に働く外国人労働者を必要としている日本の労働市場が存在するからだ。そしてめぐりめぐってそうした外国人労働者に支えられているのが私たち日本人の現在の生活なのである。難民制度にただ乗りしているのは、外国人労働者ではなく、その先に存在する私たち日本人自身である。外国人労働者の受入れ対策の遅れや、関連する政策の不在が、難民問題にひずみとなって表れている。
4 「日本は難民に冷たい国」という言説と実態
日本での難民認定率は、認定制度発足当初こそ二五%を超えたが、その後は一貫して著しく低い。日本の難民認定数は、二〇〇八年の五七人を最高とし、一桁台(二〇一三年の六人)から二桁前半を推移している。過去三年はそれぞれ、二七人、二八人、二〇人であり、申請者の激増とあいまって認定率は〇・三~〇・一%と、UNHCRのグローバル・トレンズ報告書において、特に名指しで批判されるほど低迷している。
世界の難民情勢とかけ離れた外国人労働者の流入実態を考えれば、単純な認定率を根拠とする日本批判は的外れともいえる。しかしながら、それでもなお、日本はやはり「真の難民に冷たい国」なのである。その理由の一端は、人権条約である難民条約の精神に適合しない、厳格すぎる適用にある。その証左の一つが、審査の結果、一次審査で不認定とされたものの、異議申立をして、その結果認定された人の数である。法務省によれば、これまでに条約難民として認められた七〇八人のうち、およそ二割にあたる一三二人(一八・六%)がそうした不認定とされた中から、不服申立の結果認定された人である。言い換えれば、これらの人々が不服申立を断念していたら、あるいは何らかの理由で不服申立ができなかったとしたら、日本政府は、難民条約に該当する真の難民を切り捨てていたことになる。この一三二人以外にも、不認定とされた人の中に、本来難民と認定されるべき人がいったいどれだけ混じっていることだろう。
世界の難民の潮流からかけ離れた、就労目的の申請者が多数を占める以上、不認定者(一次審査)の主な申し立て内容は、条約の趣旨に沿わない人間関係や借金をめぐる債権者とのトラブルが最も多い。しかし、申し立て理由には、政治活動(政党間の争い、非支持政党からの脅迫等)、宗教(改宗、信仰等)、人種(少数民族、差別等)、その他(カースト、兵役忌避、LGBT等)も含まれる。もちろん、ブローカーからこれらを申請理由とするよう指南された申請濫用者が存在するのはまぎれもない事実だろう(特定の政党支持を理由にしつつ、当該政党の党首の名前さえ覚えていない、改宗を理由にしつつその宗教の基礎的な知識ももたないなど)。
他方で、難民認定されるべき人々が相当数、書類の不備などが理由で不認定となっているのもまた事実である。実際、生年月日や氏名のアルファベットの誤記(母国語ではアルファベット表記をしない)すらも認定しない理由とされた事例がある。当局から深刻な迫害を受けている人は、必要な書類は揃えられず、また、もっともらしい嘘をつくこともできない。劇的な嘘はいくらでも語れるが、真実を語る人は真実しか語れないからである。
5 提言に代えて――第三国定住の活用を
UNHCRが、難民・国内避難民問題の恒久的解決策として掲げるのが、①自主的な帰還、②一次庇護国への定住、③第三国への定住という三つの選択肢である(後述のグローバル・コンパクトでは五つ)。
いうまでもなく、最も理想的な解決策とされるのが、第一の選択肢の自主的帰還であるが、難民や国内避難民が、強制されることなく、自らの意思で自発的に帰還するには、そもそも人々が国や故郷を離れざるを得なかった根本原因の解決が必要条件である。難しい課題ではあるが、日本政府には、各国政府と協力してこれを可能とするための外交努力とともに、紛争後の社会の復興、そして紛争再燃の予防のための資金提供や国際協力を国際機関経由で、さらには日本のNGO支援を通じて期待したい。
第二、第三の選択肢は、早期の、かつ根本的解決が望めず、出身国の情勢が膠着状態に陥っている際の最善ではないものの、現実的な解決策といえる。
一次庇護国への定住は、多くの場合、地理的・文化的に近い隣国や隣接地域への定住を意味している。しかし、これら庇護国は、隣国の紛争や難民の大量流入で、すでに社会的・経済的に壊滅的な打撃を受け、疲弊し、脆弱な状態にあり、こうした庇護国において、難民の定着と自立は、当事国政府や国境周辺の住民の理解とともに、諸外国からの国際協力なしにはありえない。この分野での日本政府やJICA、そしてNGOによる貢献はすでに目覚ましいものがあるが、一方では内向き志向が指摘され、国際協力予算も削減される中、さらなる拡充が課題である。納税者である国民の理解が最重要の課題であるが、「もし私が難民だったら」「もしあの難民キャンプにいるのが自分の娘だったら、孫だったら」という素朴な想像力が鍵であるように思う。
第三の選択肢は、すでに日本が実施している「第三国定住」制度である。日本政府は難民問題に関する負担や責任を適正に分担するという世界の動向を踏まえ、国際貢献及び人道支援の観点からこの制度を導入したが、その実績は既述のとおりミャンマー難民限定で三九家族一五二人である。果たしてこれが「国際貢献」といえる実績だろうか。
別表は、国別の統計が入手できる最新二年間の第三国定住受入れ数の比較である。欧米とは国の成り立ちや社会情勢が異なるとはいえ、あまりに世界の趨勢と乖離がある。難民を受け入れないという日本批判は、単純な認定率を根拠とするなら不当ともいえようが、この実績を根拠にするなら、甘んじて受けるしかないだろう。
この三九家族は、受入れ順に、三重県鈴鹿市(三家族)、千葉県東金市(二家族)、埼玉県三郷市・春日部市(ともに四家族)、千葉市(一八家族)、広島県呉市(五家族)、神奈川県藤沢市(三家族)で暮らしている。しかし、唯一の受入れ対象であるミャンマー難民にとっても日本は決して魅力的な国ではない。辞退され受入れゼロという年さえあった。しかし(受入れ数の上限約三〇人の範囲内ではあるが)昨年は、過去最多の八家族二九人が来日している。受入れた自治体や関係者の方々の尽力により、少なくとも希望者ゼロになる国ではなくなったということではないだろうか。
もはや日本だけが鎖国をすることはできない。せめてその突破口に、この第三国定住制度を活用し、対象国、人数ともに拡充することを、あらためて、多くの識者同様、私も提案したい。留学生に限定せず、家族単位でシリアはじめ、世界の難民の大勢を占める国々からの難民受入れを検討することは、東京五輪を控えた日本がまさに国際貢献国家になるための第一歩である。本年末までに、国連総会で採択見込みの「難民に関するグローバル・コンパクト」の主題は国際社会の負担と責任分担である。問われているのは日本政府のみならず、日本社会全体の責任分担である。
別表出典:UNHCR, Statistical Yearbook 2015&2016